私たちは毎日お金を使っているが、その構造と論理を本当に理解している人は少ない。
書籍『The Monetary Pyramid』の著者であるニック・バティアは、ウォール街生まれの金融実務家であり、ビットコインの研究者でもある。複雑な専門用語を使う代わりに、彼は非常に基本的な質問から始める:お金とは何か?誰がその価値を定義するのか?そして誰がその信用を維持するのか?
本書で最も中心的なアイデアのひとつは、「貨幣は何層にも重なって存在する」というものだ。金、ドル、ビットコイン、ステイブルコイン、そしてプラットフォーム・クレジットはすべて、お金を支払うように見え、「お金」と呼ばれているが、構造的にはまったく異なる。あるものは究極の資産であり、あるものは何らかの約束に対する信用の証に過ぎない。
『マネー・ピラミッド』の価値は、お金の投資方法を教えることではなく、お金の背後にあるシステム論理を解体する手助けをすることだ。私たちは統一された単一層の貨幣システムの中に生きているのではなく、構造化され、階層化され、動的に進化する「簿記秩序」の中に生きているのだと気づかせてくれる。
ローマ銀貨の物語
本書は、一見遠い歴史上の出来事、ローマ帝国のディナール銀貨から始まる。
ローマ共和国がこの銀貨を初めて発行したのは、おそらく紀元前211年のことで、地中海全域の経済システムを統合することを目的としていた。ローマ帝国成立後の紀元1世紀までに、ディナールは公式通貨となり、ヨーロッパ、北アフリカ、西アジアの広い地域を通過した。
最初に発行されたとき、ディナール銀貨は最大98%の銀を含み、1枚約3.9グラムで、裏面には皇帝の頭部と武勲のシンボルが描かれ、帝国の栄光と信用を象徴するものとして鋳造されることが多かった。この通貨は帝国軍に受け入れられたため、国際貿易の決済手段としても好まれるようになり、今日の「ドル本位制」にやや似ている。
しかし、この栄光は長くは続かなかった。帝国の拡大と財政赤字により、ディナールは徐々に「間引き」され始めたのだ。紀元2世紀のマルコ・アウレリウスの治世には、銀の含有率は80%まで低下していた。その後、インフレが進み、3世紀半ばのクラウディウス1世の時代には、銀は5%以下になり、残りはほとんどが銅や雑金属だった。外観はまだディナールのようだったが、芯はもはや銀ではなく、低品質の合金だった。
最も典型的な変化は西暦274年、ローマ皇帝アウレリアヌスが新しい硬貨アントニニアヌスを導入した時である。アントニニアヌスは、「銀貨」の名を持ち続けたが、貴金属はほとんど含まれていなかった。つまり、名目は銀貨であるが、実質はすでに銅貨であったという「フェースマネー」であった。
この過程では通貨改革は行われず、新しい硬貨も発行されず、「切り下げます」というアナウンスもなかった。すべては「名称を変えない」という前提のもと、ひっそりと行われた。人々はまだ「銀貨」を手にしていると思っていたが、徐々に買えるものが少なくなっていることに気づいた。
通貨危機は、ほとんどの場合、爆発的なものではなく、「ゆっくりとした信頼の崩壊」である。一日で破産することはないが、手元にあるお金で同じものが何年も買えなくなる。そして、あなたはそれに気づかないかもしれない。
お金は何層にも重なっている
私たちはよく「お金」の話をしますが、実は日常生活で出会う様々な種類の「お金」は同じではありません。お金」の本質は同じではない。銀行口座の残高も、手元の紙幣も、プラットフォームのポイントカードも、あるいは買ったUSDTや会社の口座のステイブルコインも、どれも「支払い」レベルでは機能しているように見えますが、本質的にはまったく違う種類のお金なのです。
本書は重要な点を指摘している:マネーはレイヤーに存在し、信用構造がレイヤーを決定する。
あなたの口座にある10万ドルの預金は、あなたが本当に10万ドルの資産を持っているのではなく、銀行が帳簿上であなたに10万ドルの借りがあるということです。あなたの手元にあるUSDTは、Tetherが将来あなたに1:1のレートで米ドルを返すことを約束するためのバウチャーです。アリペイ残高の最下層は、複数の金融機関に信託された資金の「デジタル表現」である可能性さえある。
法律や金融構造の観点から見ると、これらはすべて第2、第3の通貨であり、うまく機能しているときはいいが、取引先に問題があれば紙くずになりかねない。
だからこそ、著者はこう言うのだ。あなたは資産を所有しているつもりだが、問題のないシステムがあることを信頼しているだけなのだ。
多くの人が株やファンド、債券を保有し、それらを資産だと思っているが、実は通貨ピラミッドの観点から見れば、それらは「バランスシートの信用商品」であり、リスクのないお金ではない。
このことは、金融危機や戦争、政権交代の際に、人々が金やドル、さらにはビットコインを買いに殺到する理由を説明している!彼らは投資をしているのではなく、「約束する必要のない」資産に「最初のレベルに戻っている」のだ。
このような「レイヤー・マネー」の論理は、現代の通貨システムのいたるところで見ることができる。米ドルが世界の金融ピラミッドの頂点に位置するのも、この構造によるものだ。
ドルの覇権はどこからともなく生まれたものではなく、一連の通貨階層化メカニズムによって確立されたものだ。
第二次世界大戦がまだ終わっていなかった1944年、アメリカのニューハンプシャーにあるブレトンウッズで44カ国が会議を開き、新しい国際通貨制度を確立することを決定した。ドルは金に固定され、他国の通貨はドルに固定される。それ以降、金は第1層に位置し、ドルは「第2層の第1位」となり、他国の不換紙幣はドル以下の第3層に位置することになった。
このシステムにより、米ドルは世界的な「決済センター」となった。他国の中央銀行は金を直接準備することができず、米ドル資産しか保有できないからだ。これは、実際には、ドルは金の「代理」であり、「擬似的な第一級資産」とみなすことができると認めているに等しい。
ブレトンウッズ体制下のドルは、1971年にニクソン政府が突如「金の窓の閉鎖」、つまり金に対するドルのコミットメントの打ち切りを発表するまで、30年近く運用された。その瞬間から、ドルは正式に金のアンカーから外され、完全な信用通貨となった。
しかし、奇妙なことに、ドルの世界的地位は弱まるどころか、さらに強化された。
その理由は、第一に、ブレトンウッズ体制は終結したが、ドルは長い間、世界貿易、金融、資本決済のインフラに組み込まれてきた。第三に、ほぼすべての主要な商品(原油、食品、金属など)はドル建てであり、ドルは世界的な「価格決定単位」となっている。
したがって、今日「ドルは世界的な主権通貨である」と言うとき、それは「世界的に認知された紙幣」としてではなく、世界の通貨ピラミッドにおける「世界通貨」として言っているのである。ほとんどの国の不換紙幣、国境を越えた資産、中央銀行の準備金は、実際にはドルの「重ね鏡」なのである。
言い換えれば、世界の通貨システムを逆ピラミッドとして描くと、
この構造は法律で決められているわけではなく、数十年にわたる金融構造、資産の流れ、政策の取り決めによって徐々に固められてきた。
中央銀行の本質
今日、「中央銀行」といえば、私たちが最初に思い浮かべるのは金利、為替レート、放水などだろう。しかし、『マネー・ピラミッド』という本の中で著者は、中央銀行の最も初期の機能は「貨幣を発行すること」ではなく、「勘定を管理すること」、より正確には「勘定を清算すること」であったことを思い出させてくれる。
中央銀行の最初の機能は「貨幣を発行する」ことではなく、「勘定を管理する」ことだった。
この概念は、最初はあまり直感的に聞こえませんが、歴史的な背景を考えると、非常に理解しやすいものです。
17世紀初頭、オランダのアムステルダムは、ヨーロッパの貿易の中心地として台頭したばかりでした。バルト海、地中海、東インドを結ぶ重要な港として、国境を越えた多くの商人が毎日ここで取引をしていた。しかし、当時の貨幣制度は極めて混沌としていた。銀貨、ターラー、フロリン、金貨、異なる硬貨、異なる年号、異なる内容の硬貨が市場に流通し、取引のたびに確認、計量、釣銭をしなければならず、面倒であると同時に間違いも起こりやすい。
取引コストを削減し、決済システムを統一するため、1609年にアムステルダム銀行(Wisselbank)が設立された。この銀行のシステム設計は画期的なもので、融資も商業業務も行わず、ただひとつ、商人から預かった金貨や銀貨を受け入れ、その帳簿に「銀行預金」として記録し、以後の支払いはすべて銀行内部を通じて行われた。その後の支払いはすべて銀行内部の帳簿を通じて行われた。
これは貨幣制度において、物理的な移動から帳簿上の移動へと飛躍した最初の出来事だった。コインを移動させる必要がなくなり、銀行が帳簿を入れ替えるだけで取引が完了したのです。より効率的で、取引の信用はより一元化された。言い換えれば、
帳簿をつけ、取引の正当性を認識する者が、「お金の秩序」を支配する者を決定する。
このモデルは後にイギリスに広まり、1694年のイングランド銀行の創設に影響を与えた。
私たちが日常的に使っているお金のほとんどは、銀行預金、ペイパルの残高、地域の決済システムといった第二層であり、これらは単に商業組織があなたに債務証明書を発行しているに過ぎない。債務証明書を発行しているに過ぎない。銀行間の資金移動は、直接相互運用可能なものではなく、「ブック・マスター・ノード」を必要とする。このノードは中央銀行である。
あなたがCCBから中国招商銀行(CMB)にお金を転送するとき、実際の決済アクションは、アプリの "確認 "を指すことではなく、CCBとCMBは、中央銀行の準備口座に清算操作を完了したことです。中央銀行のシステムがなければ、取引は法的および金融システムで確立されていません。
つまり、清算システムの帳簿にアクセスできる者は、通貨システムの構造的支配力を持つことになる。
このことを理解することで、今日の非常に現実的な政策現象も理解できます:なぜ中央銀行は「中央銀行デジタル通貨(CBDC)」を推進しているのでしょうか?
多くの人は、これは単に決済の効率を上げるため、あるいはWeChatやAlipayに対抗するためだと考えている。しかし、「通貨は本の構造である」という本から、その根底にある論理、CBDCの基本的な目的は、デジタル時代の中央銀行を「最終的な帳簿管理権」の独占的な地位に再確立することである。
元のシステムでは、中央銀行は銀行と国家の帳簿のためだけであり、直接個人に向き合っていませんでした。
これは決済エクスペリエンスの強化のように見えるが、実際には決済機関の構造の変化である。CBDCは「銀行間」から「ユーザー間」へとさらに一歩踏み込み、中央銀行が「あらゆるマイクロ取引」のオーナーシップを持つことを可能にする。
ビットコインの位置づけ
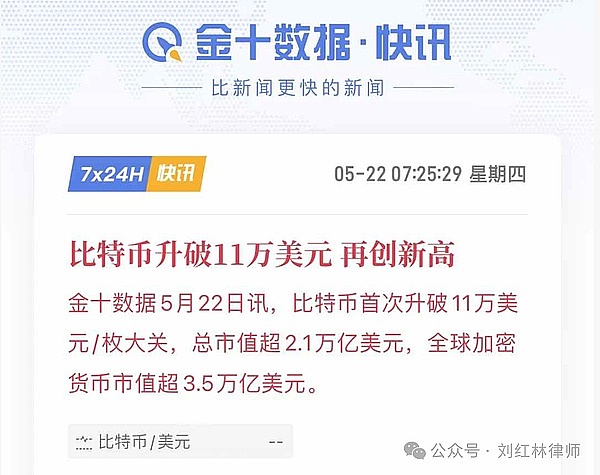
そう考えれば、なぜビットコインが「不換紙幣システムへの挑戦者」と見なされてきたのかを理解する方が自然だ。通貨システムへの挑戦者。
ビットコインの本質は、単に新しい資産を生み出すだけでなく、非中央集権的な台帳構造を提案し、誰が帳簿をつけるのかという疑問に対する根本的な対応である。それは「誰が帳簿をつけるのか」という疑問に対する根本的な回答だ。
ビットコインネットワークは、誰もが小銭として使えるように設計されたのではなく、中央集権的な機関に依存せず、第三者への信頼を必要とせず、誰もが検証できる価値を記録するシステムとして設計された。中央銀行や政府に記帳の権利を与えないのであれば、他の選択肢はないのか?
その答えはブロックチェーンだ。
ビットコインのシステムでは、すべての取引がネットワーク全体にブロードキャストされ、ネットワーク内のすべてのノードが、銀行に頼ることなく、中央銀行に頼ることなく、プラットフォームに頼ることなく、取引が正当であることを検証できる。これは「規制緩和」ではなく、「分散型簿記ルール」である。
著者は本書の中で、ビットコインの地位を誇張しすぎることなく、むしろ冷静に、第一階層通貨としてのビットコインの意義は、それが「世界通貨」になるかどうかではなく、むしろ「世界通貨」を構築することにあると指摘している。"ではなく、むしろ国家の信用に頼らない決済構造を構築することである。
取引をチェーン上に送信し、ネットワークがそれを確認する限り、取り消したり、改ざんしたり、拒否したりすることはできない。この「最終性」は、まさに中央銀行の決済システムが長い間独占しようとしてきた能力だ。ビットコインは、「最終性」をオープン・プロトコルのコンセンサス結果とすることで、その独占を打破する。
そして、このコンセンサス台帳の上に、第2、第3層の構造も生まれ始めている。BTCを担保として発行されるステーブルコイン、支払いを加速するゲートウェイとしてのライトニングネットワーク、さらには金利や預金を提供する「ビットコイン銀行」。そして、金利や預金サービスを提供する「ビットコイン銀行」までもが登場している。ビットコインはピラミッドから脱却したのではなく、独自のピラミッド構造を構築したのだ。
これは、先ほどお話ししたCBDCとは正反対のように見えるかもしれませんが、実は同じ核心的な問いに応えているのです:デジタルの世界でも通用する「通貨元帳」をどう構築するか?一方は国家システムに依存し、もう一方はネットワーク・プロトコルのコンセンサスに依存する。両者は単純な競争ではなく、2つの「簿記の正しい論理」のゲームなのだ。
政府と銀行を信じるか、数学とコードを信じるかを選ぶことができる。そしてそれこそが、ビットコインが重要である根本的な理由なのです。
ステーブルコインの妥協
ビットコインは分散化とトランザクションの不変性に重点を置いて設計され、その結果、転送速度とスループットを犠牲にしています。分以上かかる。また、オンチェーン処理手数料(Gas)の価格も、ネットワークの混雑によって劇的に変動するため、日常的なマイクロペイメントシナリオでの利用は制限される。
現実世界のニーズは、ステーブルコインという異なる構造の出現につながりました。
ステーブルコインは、USDT(Tether)、USDC(Circle)など、不換紙幣(主に米ドル)に固定された中央機関によって発行されるデジタル資産です。これらは「ビットコインと戦う」ことを意図しているのではなく、通貨のレイヤーとしてビットコインの「非スケーラビリティ」を補完し、その上により便利で変動の少ない決済レイヤーを構築することを目的としている。
トレーダーがBTCやETHの急激な変動に対して一時的に「ヘッジ」できるように、明確な価格アンカーを持っています。は数秒から数分で完了します。資金移動の敷居が低く、オンチェーンDeFi、ゲーム、国境を越えた送金シナリオに特に適しています。
これこそが、世界の暗号市場でステーブルコインが急速に支持を集めている理由であり、2024年初頭には、毎日のオンチェーンでのステーブルコイン取引量が数百億ドルに達し、1000億USDT以上が流通し、多くの新興市場国で米ドルの「事実上の代替」となっています。USDTは多くの新興市場国で「米ドルの事実上の代替品」となっている。ナイジェリア、アルゼンチン、ベネズエラなど、現地通貨が著しく切り下げられた国では、多くの人が中央銀行よりも中央集権的なステーブルコインを信頼している。
ビットコインが「デジタルゴールド」だとすれば、ステーブルコインは「チェーン上の銀行預金」だ。それらは本質的に第二層通貨であり、無条件で利用可能な資産ではなく、むしろ発行者の信用に預けた信頼なのです。あなたの手元にあるUSDTやUSDCは、あなたがTetherやCircleを信頼し、それに相当する米ドルが銀行口座に準備されている場合にのみ価値があります。
ステーブルコインは、チェーン上の伝統的な金融ロジックの継続であり、現実世界の規制構造、コーポレートガバナンス、法的契約を使用して、チェーン上の暗号資産のフローを提供します。純粋な暗号技術革新ではなく、「制度的適応の産物」なのだ。
ステーブルコインは、暗号通貨ピラミッドの「第2層」に位置する中央集権型の負債通貨である。ステーブルコインのリスクは、「カウンターパーティ・リスク」の範疇に留まることだ。1:1のドル準備金が本物であることを直接確認することはできませんし、極端な状況下で発行者が資産を「凍結、検閲、支払い拒否」するかどうかをコントロールすることもできません。
信託の構造を見てみると、支配的なアプローチの違いは実は非常に明確です:
どちらもコインのように見えますが、その背後にはまったく異なる信頼ロジックと台帳アーキテクチャがあります。どちらを使うかは、実際に誰を信頼し、誰が帳簿を管理するかを選ぶことになります。ここがstablecoin、ビットコイン、CBDCが本当に分かれるところです。
エンディングノート:マネーの再理解
私たちは、マネーは国家によって定義された均一なものであり、口座の数字であり、財布の残高であり、銀行カードであり、元であり、ドルであり、銀行口座であり、財布であり、銀行口座であり、財布であり、財布であり、財布であると考えました。しかし本書を読めば、通貨は実際には階層化され、構造化され、信頼のマッピングであることに気づくだろう。
単なる紙幣ではなく、「アクセス」を与えるシステムなのだ。つまり、どの階層にいるのか、どの種類を保有しているのか、誰が、何を、どの本で信用しているのか、ということだ。単なる紙幣ではなく、「アクセス」を与えるシステムなのだ。つまり、自分がどの階層にいるのか、どの種類を保有しているのか、誰を信頼しているのか、何を頼りにしているのか、何のために帳簿をつけているのか、ということだ。
つまり、未来の世界は「ひとつの通貨」の世界ではなく、「共存する本」の世界なのかもしれない。公共料金の支払いにCBDCを使うという国家を信じる人もいれば、国境を越えたビジネスをするために安定したコインを使うという市場を信じる人もいる。
これらは代替案ではなく、展開されつつある新しい構造である。テクノロジーは、誰が帳簿をつけるかという可能性を開き、お金とは何かを再定義した。お金とは何か?
貨幣がもはや単一のセンターによって発行されることも、紙に印刷されることも、銀行口座に保管されることもなく、コードの中、アドレスの中、そしてチェーン上のすべての検証されたブロックの中に存在するとき、私たちが本当に直面しているのは、新しい通貨の台頭ではなく、新しい帳簿なのだ。選択の台帳である。
 Weatherly
Weatherly
 Weatherly
Weatherly Catherine
Catherine Weatherly
Weatherly Anais
Anais Catherine
Catherine Kikyo
Kikyo Joy
Joy Catherine
Catherine Weatherly
Weatherly Kikyo
Kikyo